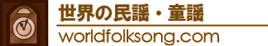手のひらを太陽に 歌詞と解説
当初のブラジル音楽「バイヨン」版はあまり人気が出なかった?!
「ぼくらはみんな 生きている 生きているから 歌うんだ」が歌いだしの『手のひらを太陽に』。作詞はアンパンマン作者の「やなせたかし」、作曲は、『見上げてごらん夜の星を』で知られる「いずみたく」。
歌詞では、ミミズ、オケラ、アメンボから、トンボ、カエル、ミツバチ、そしてスズメ、イナゴ、カゲロウまで、小さな昆虫から小鳥まで、小さな生き物が「みんな みんな 生きているんだ 友だちなんだ」と歌い上げる生命讃歌となっている。

1961年に日本教育テレビ(現:テレビ朝日)で放送された『手のひらを太陽に』は、当初はあまり反響は少なかったという。
さらに翌年の1962年にNHK「みんなのうた」でも放送されたが、それでも大きなヒットにはならなかったようだ(歌は宮城まり子)。
【YouTube】手のひらを太陽に
歌詞
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 歌うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから かなしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮(ちしお)
ミミズだって オケラだって
アメンボだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだぼくらはみんな 生きている
生きているから 笑うんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから うれしいんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
トンボだって カエルだって
ミツバチだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだぼくらはみんな 生きている
生きているから おどるんだ
ぼくらはみんな 生きている
生きているから 愛するんだ
手のひらを太陽に すかしてみれば
まっかに流れる ぼくの血潮
スズメだって イナゴだって
カゲロウだって
みんな みんな生きているんだ
友だちなんだ
最初は何故ヒットしなかった?
なぜ最初期の『手のひらを太陽に』はあまりヒットしなかったのだろうか?
その理由の一つとしては、最初期の『手のひらを太陽に』にはブラジル音楽風のアレンジが加えられていたことが遠因として考えられる。
この「ブラジル音楽風」とは、1950年代に世界中でブームとなったダンス音楽「バイヨン」のリズムが軽く取り入れられたアレンジを意味している。
ブラジル音楽「バイヨン」のリズムとはどんなリズムなのか。最も分かりやすい例で言えば、アニメ「サザエさん」エンディング曲のあのリズムがそれに近い(全く同じではないが、おそらくルーツは同じ)。
「サザエさん」エンディング曲とバイヨンの関係については、こちらのページ「サザエさん エンディング曲の元ネタ・ルーツ ブラジル音楽「バイヨン」」で解説しているので是非お立ち寄りいただきたい。
さて、最初期の『手のひらを太陽に』は実際にどんなアレンジだったのか?当時の音源が「NHK みんなのうた 50 アニバーサリー・ベスト ~おしりかじり虫~」に収録されている。Amazonで一部視聴可能だが、分かりにくいかもしれない。
バイヨン風が軽く取り入れられたリズムに乗せて、宮城まり子の歌で『手のひらを太陽に』が歌い上げられている。もちろんこのバイヨン版も悪くはないが、現在一般的な素直なリズムに比べると若干ひねった印象を受ける。全年齢の家庭向けソングとしては立ち位置が若干微妙だ。
これに対して、1965年に男声コーラスグループのポニージャックスがカバーした『手のひらを太陽に』は、現代版に近い素直なリズムのアレンジで、健全さ・爽やかさがより強調された全年齢向けのアレンジとなっている。これなら老若男女にすんなり受け入れられやすい。
ポニージャックス『手のひらを太陽に』は大ヒットを記録。同年のNHK紅白歌合戦でも同曲が披露されたほどだ。決め手はやはり素直なリズムのアレンジが採用されたことにあると思われる。
関連ページ
- バイヨン ブラジルのダンス音楽・リズム
- サンバと同じブラジル北東部発祥の民族音楽
- サザエさん エンディング曲の元ネタ・ルーツ ブラジル音楽「バイヨン」
- 国民的アニメ「サザエさん」エンディング曲のルーツを探る
かわいい動物のうた
- 雀のうた スズメに関する民謡・童謡
- 『雀の学校』、『すずめのお宿』、『砂山』など、かわいいスズメが歌に出てくる世界の民謡・童謡まとめ
- 動物のうた
- イヌ、ネコ、うさぎ、くまなど、可愛い動物が歌詞に登場する世界の民謡・童謡、日本の唱歌、動物に関連する歌、動物をテーマとした曲・クラシック音楽など動物別まとめ