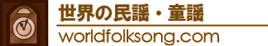ミネソタの卵売り 歌詞と解説
コッコッコッコッ コケッコー♪ なぜタマゴ売りなのか?
『ミネソタの卵売り』は、1951年リリースの日本の歌謡曲。作詞:佐伯孝夫、作曲:利根一郎、歌:暁テル子。「コッコッコッコッ コケッコー♪」の歌い出しで有名だ。

日本がアメリカに占領されていた時代の古い歌謡曲である同曲。今日注目される機会があるとすれば、それはテレビ番組「笑点」で林家 木久扇(はやしや きくおう)によりネタにされる場合にほぼ限定されるだろう。
【YouTube】ミネソタのたまご売り/暁テル子
歌詞
ココココ コケッコ
ココココ コケッコ
私はミネソタの卵売り
町中で一番の人気者
つやつや生みたて 買わないか
卵に黄味と白味がなけりゃ
お代は要らない
ココココ コケッコココココ コケッコ
ココココ コケッコ
私はミネソタの卵売り
町中で一番ののど自慢
私のにわとり素敵です
卵を生んだり お歌のけいこ
ドレミ ファ ソラシド
ココココ コケッコココココ コケッコ
ココココ コケッコ
私はミネソタの卵売り
町中で一番の美人です
皆さん卵を喰べなさい
美人になるよ いい声出るよ
朝から晩まで
ココココ コケッコ
ミネソタに卵売りはいない?
曲名を見ると、まるでアメリカのミネソタ州に実在する卵売りが元ネタになっているかのような印象を受けるが、おそらくはミネソタ州に卵売りはいないだろうし、アメリカ全土を見てもそれは同じであろう。
実在するモデルがないとしたら、一体なぜミネソタなのか?なぜ卵売りなのか?
この謎についてネットで調べると、次のような解説を見かけた。
米国ミネソタに卵売りの習慣はないらしい。 作詞・佐伯孝夫の家にミネソタ州からお客が来た時に卵売りがやってきたというのが最有力説のようです。
これについては根拠となる客観的な資料が示されていなかったため、真否のほどは定かではない。
「〇〇売り」シリーズ三部作の最後
まずおさえておかなければならないのは、『ミネソタの卵売り』は、暁テル子「〇〇売り」シリーズ三部作の最後の作品であったという点である。
当時ビクターレコードから発売された暁テル子の「〇〇売り」シリーズ三部作は次のとおり。
1950年5月『リオのポポ売り』
1950年8月『チロルのミルク売り』
1951年2月『ミネソタの卵売り』
半年ごとに1曲のペースで、海外の地名を冠した「〇〇売り」シリーズの楽曲がリリースされていたことが分かる。
リオはブラジル、チロルはオーストリア南部(イタリア北部)。「ポポ」は落葉高木の「ポーポー Pawpaw」か。
アメリカのミネソタが選ばれた理由とは?
『ミネソタの卵売り』がリリースされた1951年2月の日本は、まだ連合国軍GHQによりアメリカの占領下にあった。サンフランシスコ講和条約により日本が独立を果たすのは1951年8月のこと。
講和条約締結へ向けてアメリカと日本の融和ムードが高まる中、暁テル子の「〇〇売り」シリーズ三部作の最後を飾る曲としてアメリカの地名が用いられるのは自然な流れといえる。
そして当時のアメリカを象徴する音楽といえばジャズ。暁テル子にジャズ歌謡を歌わせるにあたり、参考とすべきアメリカの女性ジャズ・ポップス歌手といえば、当時人気が高かったのは、ミネソタ出身のアンドリューズ・シスターズ(The Andrews Sisters)だ。
このようにして、アメリカのミネソタという地名が曲に用いられることになったのではないかと推測される。
流入したアメリカ文化とタマゴ
残された疑問は、ミネソタとタマゴがどうつながるのかだが、このタマゴというキーワードは、ミネソタの方にかかるのではなく、ミネソタを含むアメリカ全体の食文化に関係しているように思われる。
アメリカの朝食では、カリカリに焼いたベーコンと目玉焼き、またはスクランブル・エッグなどの卵料理がよく見られるが、これらがGHQ占領下の日本でも提供され、アメリカの食文化として認識が広まっていたと想像できる。
もちろん日本の朝食でもタマゴ料理はあっただろうが、アメリカの食文化としてタマゴが目新しく見えた時代だったのではないだろうか。
ミネソタを含むアメリカ全体の象徴として、この「タマゴ」というキーワードが組みこまれ、「〇〇売り」というフォーマットにそのまま機械的に当てはめられたため、「卵売り」というありそうでなさそうなフレーズが誕生したのだろう。
タマゴは栄養があるので、戦後食糧難における国民食として摂取を進める宣伝ソングの意味合いもあったのかもしれない。
もしかしたら、参考にしたジャズのリズムが「コッコッコッコッ コケッコー」に空耳で聞こえ、そこからタマゴ売りを思いついたなんてことも想像できる。
最終的にはレコード会社か作曲者の公式見解を待つしかないが、 アメリカ→ジャズ→アンドリューシスターズ→ミネソタの流れは結構当たっているのではないかと思われる。皆さんはいかがお考えだろうか?
関連ページ
- にわとりのうた・ひよこのうた
- 『トトトのうた』、『いいやつみつけた』、『かわいいかくれんぼ』、『夜が明けた』など、にわとりやひよこに関する日本の民謡・童謡・世界の歌まとめ。
- 動物のうた
- イヌ、ネコ、うさぎ、くまなど、可愛い動物が歌詞に登場する世界の民謡・童謡、日本の唱歌、動物に関連する歌、動物をテーマとした曲・クラシック音楽など動物別まとめ