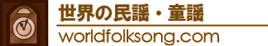チャンチキおけさ 歌詞と解説 三波春夫
夜の屋台で 安酒あおり 小皿たたいて おけさ節
『チャンチキおけさ』は、三波春夫が1957年6月に歌謡界へ名乗りを上げたデビュー曲。200万枚を超える大ヒットを記録し、一躍人気歌手の仲間入りを果たした。今日では、夏祭りの歌・盆踊りの曲としても親しまれている。

戦後4年間のシベリア抑留から解放された三波春夫は、浪曲師・南篠文若(なんじょう ふみわか)として活動していたが、演歌大衆歌謡が流行し始めていた新たな時代の流れを読み取り、芸名を「三波春夫」と改め歌謡界へ名乗りを上げたのだった。
デビュー曲である『チャンチキおけさ』の歌詞では、故郷を離れて働く出稼ぎ労働者らが、路地裏の屋台で安酒をあおりながら、遠い故郷に思いをはせて、しがない我が身のやるせなさにため息をつく男たちの人生の悲哀が描かれている。
【YouTube】盆踊り チャンチキおけさ
歌詞
月がわびしい 露地裏の
屋台の酒の ほろ苦さ
知らぬ同士が
小皿叩いて チャンチキおけさ
おけさ切なや やるせなや一人残した あのむすめ
達者でいてか お袋は
済まぬ すまぬと
詫びて今夜も チャンチキおけさ
おけさ おけさで 身をせめる故郷(くに)を出る時 持って来た
大きな夢を さかづきに
そっと浮べて
もらすため息 チャンチキおけさ
おけさ涙で くもる月
チャンチキとは?どんな意味?
「チャンチキ」とは、皿のような形をした金属製の打楽器(下写真)。摺鉦(すりがね)、当たり鉦(がね)、コンチキ、チャンギリなどとも呼称される。阿波踊りでも用いられている。

『チャンチキおけさ』では、酔っぱらった男たちが屋台で出された料理の小皿を打楽器のようにハシで叩いて調子を取る様子から、打楽器「チャンチキ」の名が歌詞や曲名取り入れられたのだろう。
おけさとは?どんな意味?
「おけさ」とは、『佐渡おけさ』に代表される新潟県民謡「おけさ節」を指しているものと思われる。炭鉱夫や船乗りたちの悲哀が歌い込まれる「おけさ節」だが、三波春夫『チャンチキおけさ』にもそういった労働者たちのやるせなさや哀しみが表現されており、同曲は歌謡曲版にアレンジされた「おけさ節」といった位置づけになるのだろうか。
ちなみに、どういった由来で「おけさ節」という奇妙な曲名がつけられたのかについては、まことしやかな諸説が入り乱れ真相は定かではないが、一説によれば、江戸時代後期に新潟で船乗り相手の芸妓をしていたお桂さん(おけいさん)という女性を詠んだ甚句がルーツと説明されることがあるようだ。
関連ページ
- 佐渡おけさ 新潟県民謡
- 佐渡へ佐渡へと 草木もなびくヨ 佐渡は居よいか住みよいか
- おけさ 意味・語源・由来
- 猫の恩返し?娘の名前? 諸説入り乱れるルーツまとめ
- 夏祭りの歌・盆踊りの曲
- 『東京音頭』、『東京五輪音頭』、『花笠音頭』など、有名な夏祭り・盆踊りの歌まとめ